
SEO対策とは?SEOで上位表示する効果的な施策と事例
SEO対策
2024.04.26
2020.01.08
2023.09.15
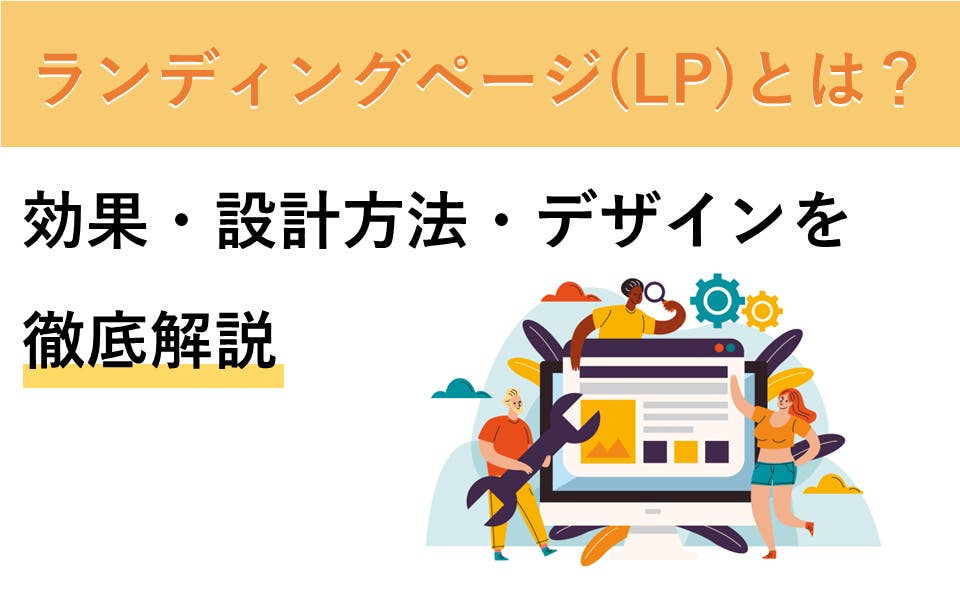
近年、EC市場の拡大やスマートフォン利用者の増加に伴い、インターネット広告市場は拡大し続けています。2023年のインターネット広告費用は、1兆7,589億円までに成長しており、地上波テレビ広告費の1兆7,848億円に迫ってきています。
インターネット広告市場が拡大しているということは、広告の受け皿となるランディングページのニーズも当然ながら高まってきていると言えます。
広告費をつぎ込み集客ができたとしても、集客先であるランディングページが魅力的でなければ、コンバージョンには繋がらず、結果的に売り上げにはインパクトしません。
インターネット広告を効果的に運用していく上で、ランディングページはとても重要です。インターネット広告と合わせてランディングページは最適化していくことで、より効果を高めることができます。このランディングページ最適化のことを、LPOと言います。
今回は、そんなランディングページの効果を高めるためのデザインについてお話ししていきます。
ランディングページ(Landing Page/LP)とは、検索結果やWeb広告などを経由してサイト訪問者が最初にアクセスするページのことを指します。
下層ページを持つWebサイトの場合、サイトの中で、ユーザーが最初にアクセスしたページがトップページであれば、トップページがランディングページとなります。
企業情報ページに最初にアクセスしたのであれば、企業情報ページがランディングページとなります。
しかし、上記は広義的な意味でのランディングページです。
一般的に使われているランディングページは、インターネット上で配信されている広告を経由して訪れたユーザーの着地先である縦長レイアウトの1ページ完結型サイトのことを指します。
一般的なWebサイトは、トップページから複数の下層ページに分岐しており、情報の抜け漏れがないように網羅的に構成されています。
しかし、ランディングページの場合は、通常サイトのような下層ページは存在しません。
ページの目的に合わせて必要な情報だけを厳選し、1ページで問合せ・資料請求・購入を促すことができるように構成されているのです。
以下の図が、サイトとランディングページの違いです。
ランディングページは、Webサイトの最初のページであり、ユーザーが最初に訪れるページです。ホームページは、Webサイトの全体的な概要を示すページです。
ランディングページは、Webサイトの最初のページとして、ユーザーを惹きつけるようなコンテンツを提供することが重要です。ランディングページでは、サービス内容や特徴、数値などを明確に伝えることが重要です。そして、そこから商品を販売することが目的となります。
一方、ホームページは、会社の特徴を記載します。ホームページでは、サービス内容や特徴、数値などを紹介するだけでなく、ユーザーがサービスを使用して何ができるのかをより詳しく伝えることが重要となります。
つまり、ホームページとランディングページは役割が異なります。
一般的なWebサイトには、様々な目的を持ったサイトが存在します。
例えば、企業の顔として自己紹介の役割を持つ「コーポレートサイト」や、企業や商品の世界観を伝えるための「ブランディングサイト」、人を採用することを目的とした「採用サイト」などがあります。
そのようなサイトと比べると、ランディングページの目的はいたってシンプルです。
ランディングページの目的は、広告を経由してページに訪れたユーザーに「お問い合わせ」や「資料請求」などのコンバージョンを得ることです。
階層式のコンテンツと遷移(リンク)で成り立っている一般的なホームページの構成とは違い、LPは1ページ完結型の構成になっていると前述で解説をしました。LPはCVに必要な情報のみを厳選して掲載し、ページ遷移によるユーザーの離脱を防ぐ仕組みになっています。また、ユーザー心理を分析し、購入を後押しする情報の配置が重視されます。
一般的なホームページと違い下記がLPの特徴となります。
一般的なホームページの作りの場合、リンク先を複数設定し導線を作ることでユーザー滞在時間を長くすることができます。一方で、ランディングページにはリンク先は入力フォーム1か所しかありません。
問合せや購入などを促すため多種多様な情報を提供する必要があるので、コンテンツのボリュームが増えます。また、1ページものではなくページを分割すれば、他ページへのユーザーの離脱の可能性もあるのでランディングページは1ページ縦スクロールで構成されています。
画像を多用する理由は、ページを読みやすくするためです。一方で流し読みされやすいとデメリットもあるので、画像中心で構成するにしても、ユーザーにじっくり読ませたい箇所はテキストで補足するとより良いです。
キャッチコピーや権威性を示すメディア実績などが目立つようにデザインされ、ユーザーの興味関心をかりたてるようになっています。
ランディングページはコンバージョンとなるお問合せや購入を獲得するために特化したページです。そのため、ユーザーにコンバージョンを求める問合せや購入ボタンは視覚的に目立つように大きく赤や緑といった認知しやすいカラーとなって配置されています。また、ユーザーがコンバージョンしやすいようにページの複数箇所にボタンが配置されています。
ランディングページの目的が、コンバージョンの獲得と明確なので、制作をする際は、どれだけコンバージョンが獲得できるページにするかが重要となってきます。
いくら格好良いデザインであっても、いくら情報整理ができているページであっても、コンバージョンがとれなければ良いランディングページとは言えません。
では、どのようなランディングページが、コンバージョンを獲得することができるのかと疑問でしょう。
ランディングページには、広告を目にして、広告の内容に興味を持ったユーザーが流入してきます。
つまり、ユーザーは表示された広告に惹かれて、商品やサービスについて詳細が知りたいと感じていると言えます。
その知りたいという要求に対しての解答を、ランディングページ上に準備できているかどうかが、良いランディングページかどうかを判断する基準の一つになります。
ランディングページは1ページに情報をまとめているページであるため、手軽に制作できるものと思われがちですが、いざ制作を進めていくと簡単ではありません。
ランディングページを制作する時に、何も考えず、行き当たりばったりで進めてしまうと、作業の効率が悪くなるだけでなく、効果の出ないランディングページが出来上がってしまいます。
LPOを行うことで効果を出していくことは可能ですが、折角ランディングページを制作するのであれば、設計段階から効果を出せるように考えることが大切です。
そのためには、全体の流れを把握しておく必要があります。
※LPO(Landing page optimization = ランディングページ最適化)とは、ランディングページの効果を高めるため、ページのデザイン・レイアウト・テキストを、調整する作業を言います。
先ほど述べたように、ランディングページの最終目的はページに訪れたユーザーに定めたコンバージョンをしてもらうことです。
その最終目的を達成することを念頭に置きながら、全ての工程を進めていく必要があります。
一般的なランディング制作の流れは以下になります。
それぞれの工程で何をしていくのか、詳細を説明します。
戦略設計では、これからプロモーションしようとしている商品やサービスにとって、どのようなランディングページが必要なのかを考えていきます。
そのために、
・どのようなユーザーがランディングページに訪れるのか
・ユーザーに何を伝えたいのか
・ユーザーにどのような行動を起こしてもらいたいのか(コンバージョンポイント)
などを、明確にしていきます。
また、競合となりうる商品やサービスのランディングページが、どのような訴求をしているのか、どのようなコンバージョンポイントを用意しているのかを調査する必要があります。
競合を調査することは、自社のランディングページを制作するための参考にするだけでなく、競合と自社を差別化をするためにも必要です。
競合他者が、どのようなユーザーに対して、どのような施策を行なっているのかをあらかじめ頭に入れておきましょう。
ユーザー目線になって競合と自社を比較することで、今まで気がつかなかった自社の商品やサービスの魅力発見にもつながります。
情報設計とは、ランディングページを作る上で必要な情報を整理することです。
ここでは、戦略設計で想定したユーザーやコンバージョンポイントに合わせて、全体のストーリーを設計し、またそのストーリーに必要なコンテンツの情報を具体化し、最終的にその内容をワイヤーフレームに落としていきます。
ストーリーを設計する際は、「どのようなサービスなのか。」「誰のためのサービスなのか。」「サービスを受けた時にユーザーにはどんなメリットがあるのか。」「競合との違いは何なのか。」といった、ユーザーに伝えるべきポイントを洗い出し、それらの話をどういった順番で提示するかを決めていきます。
この時に重要なのは、いかにユーザー目線になって考えられるかです。
どのような順番で情報を提示すればユーザーが欲しい情報に到達でき、結果コンバージョンに至るのかを考えていきます。
提示する順番が決まったあとは、コンテンツごとに見出しや本文などのテキスト内容を決めていきます。
テキストの内容まで詰めることができたら、そのテキストを元にレイアウトを詰めていきましょう。
この時のレイアウトとは、情報の強弱をつけたり、グループ化をしたりと言う意味で、あくまでの情報整理のためのレイアウトです。
この段階でワイヤーフレームに落とし込むことをオススメします。
ワイヤーフレームはデザインをする上での設計図となるので、テキスト内容以外のグラフやイラストに必要な数値データなども用意します。
ワイヤーフレームが出来上がったら、いよいよデザインです。
ただし、すぐに作業に入るのは危険です。
まずは、ワイヤーフレームを読み込み、全体の流れを理解していきます。
その上で、デザインのトンマナやレイアウトなどの全体的な方向性を考え、完成イメージが浮かんでから作業にはいりましょう。
私のオススメは、手書きでデザインラフを描くことです。
ワイヤーフレームはあくまでも情報整理を目的としたものなので、それぞれの情報をよりわかりやすく表現するためにどのようなデザインにするか、ラフを描くことで、頭の中を整理し、作業をスムーズに進められます。
デザインが完成したら、コーディング作業に入っていきます。
ランディングページ制作の中で、コーディングは最後の工程であるため、ここでのクオリティがランディングページ全体の品質に影響します。
基本的な動作の不具合がないか、レイアウトの崩れがないかを確認するだけでなく、ユーザーの目線からみて、使いやすいページになっているかを意識して組んでいきます。
なので、見た目以外の表示速度であったり、フォームの動作も、良いランディングページの判断基準の一つとなります。
実際に自分がランディングページに訪れたユーザーと仮定し、ページをみたときにストレスがないかを確認しましょう。
ランディングページの基本的な理解ができたところで、効果のでるデザインのポイントをお話していきます。
ランディングページ制作の流れを見ていくと、効果の出るランディングページ制作をするためには、デザインだけでなくその前段階の設計が重要ということはおわかりいただけたでしょうか。
ページに訪れるユーザーや、商品・サービスによって細かなデザインは異なってきます。
今回は、コンバージョンに大きく影響すると言われている「ファーストビュー」「コンバージョンエリア」「フォーム」の3つのエリアにおいて、デザインをする際に気をつけるポイントをお伝えします。
ファーストビューとは、ページに訪れたユーザーが初めてみる画面のことを指します。
ファーストビューの役割はユーザーの心を掴み、ファーストビュー以下のコンテンツを読んでもらうためのきっかけ作りです。
デザインをするときに気をつけるポイントは、訪れたユーザーが一目見て、何のサイトなのかがわかるようにすることです。
ファーストビューに載せる要素は優先順位をつけて、極力少なくした方が訴求力の高いファーストビューになると言われています。
少ない情報でいかにユーザーに伝えたい内容を伝えるかが重要なので、キャッチコピーの見せ方や、掲載する画像はこだわりましょう。
コンバージョンエリアとは、ユーザーをランディングページの目的(コンバージョン)に促すための、行動を後押しするテキストや、行動を起こすためのボタンを配置するエリアのことを指します。
デザインをするときに気をつけるべきポイントは、他のどの要素よりも目立たせるということです。
ランディングページは他のWebサイトと比べ、情報量が多く長いため、コンバージョンエリアが目立たないと、ユーザーの目に留まらず読み飛ばされてしまうこともあります。
他のどの要素よりも目立たせる方法はいくつかあります。
まずは色です。ランディングページで利用しているメインカラーと同系色は避け、印象に残るカラーを選びましょう。
次に大きさですが、エリアを広く取って差をつけましょう。
その他には、他の要素にはない装飾を施す方法などもあります。
ユーザーがランディングページでコンバージョンするためには、コンバージョンボタンを押した後、エントリーフォームに記入する必要があります。
最後の最後でユーザーを離脱させないために、エントリーフォームのデザインはかなり重要となってきます。
デザインの際気をつけるポイントは、使い勝手を考えユーザーにストレスを与えないかということです。
入力項目が多かったり、入力がしづらかったり、ユーザーがストレスを感じるようなポイントは全て潰していきましょう。
また、デザインとは離れますが、ユーザーにストレスを与えないためには、システム部分での工夫も必要です。
・どの項目が必須なのか一目でわかるようにする
・入力漏れがある場合は、リアルタイムでエラーを表示する
・入力補助を行う
など、ユーザーの入力時の手間を減らすようにしましょう。
次に、ランディングページを制作する際のコツを4つ紹介します。
ランディングページを制作する際には、強いアイキャッチを心がけることが重要です。アイキャッチとは、ユーザーを惹きつける要素であり、そのページのテーマを表すものです。
アイキャッチは、視覚的な要素、タイトル、キャッチコピーなどを組み合わせて作成します。例えば、「あなたの夢を叶えるために、私たちができることをご紹介します」というキャッチコピーと、それに合った画像を使用して、夢を叶えるイメージを強く演出するものがアイキャッチとなります。
ランディングページを制作する際、ユーザーの視点を忘れないことが重要です。ユーザーが最初に見るのは、ランディングページのデザインやコンテンツなので、それらをわかりやすく、見やすく、興味を引くようなデザインにする必要があります。
また、ユーザーが目的を達成できるようなコンテンツを提供することも重要です。例えば、ユーザーが購入を検討している場合、商品の詳細情報や特徴を明確に伝えることで、購入意欲を高めることができます。また、ユーザーが検索している情報を提供することで、信頼性を高めることが可能です。ユーザーの視点を忘れず、わかりやすく、見やすく、信頼性の高いランディングページを制作することが重要です。
ランディングページを制作する際のコツとして、入力フォームを最適化することが重要です。フォームをわかりやすく、分かりやすく、そして効率的に作成することで、ユーザーの体験を向上させることができます。
まず、必要な情報を最小限に抑えることが重要です。ユーザーが入力しなければならない情報を最小限に抑えることで、ユーザーが入力を完了するまでの時間を短縮できます。
次に、入力フォームをわかりやすくすることが重要です。ユーザーが入力する情報を明確にするために、入力フォームの各項目に適切なラベルを付ける必要があります。また、入力フォームの各項目のフォーマットを提示することで、ユーザーが入力する情報を正しく入力できるようになります。例えば、電話番号を入力する際には、「(###) ###-####」のフォーマットを提示するなどすることで、ユーザーは電話番号を入力すれば良いと視覚的に理解できるため、使いやすい入力フォームに仕上がります。
また、入力フォームの自動補完機能を搭載することで、ユーザーが入力する手間を省くことができます。
ランディングページを定期的に更新することは、ユーザー体験を向上させるために重要です。最新の情報を常に提供することで、ユーザーが最新の製品やサービスを知ることができます。
また、新しい機能を追加したり、既存の機能を改善したりすることで、ユーザーがより使いやすいサイトを提供することができます。加えて、SEO対策にも効果的なため、定期的に更新することをおすすめします。
参考資料を用意することで、ランディングページを作成する際に必要な情報を収集したり、検証したりすることができます。
参考資料として扱えるのは、企業のミッションステートメントやビジョン、ターゲット顧客の調査結果、コンテンツマーケティング戦略などが挙げられます。また、ランディングページを作成する際には、訪問者がどのような行動を取るかを考慮したデザインを用意する必要があります。そのため、ユーザーエクスペリエンス(UX)デザインなどの専門家からのアドバイスも参考資料として活用することができます。
参考資料を用意することで、ランディングページを作成する際に必要な情報を収集したり、検証したりすることができます。また、ユーザーのニーズに応えるようなデザインを作成することも可能になります。
ランディングページを制作する際は、いくつか注意すべきポイントがあります。目的を達成できるランディングページを作り出すために、知っておくべき注意点について解説します。
ランディングページを制作する際は、商品の販売促進や集客、お問い合わせの増加など何かしらの目的があるはずです。ライティングを行う際はランディングページを制作する目的に沿って構成を行い、最後まで一貫した流れで訴求を行うことが重要です。
しかし商品のよさをアピールしたい気持ちからつい熱が入り、どのような人に向けて何を伝えたいのかわからない内容になってしまうケースも少なくありません。
常にユーザーファーストで作ることや、ユーザーのベネフィットを優先的に伝えることを意識したライティングを行うことが重要です。うまく伝えられない場合は、ランディングページを専門とするライターに、執筆依頼することも検討するとよいでしょう。
ランディングページに限った話ではありませんが、商材やサービスを紹介する際は、適切な文言が用いられているか確認することが大切です。特に化粧品や健康食品などで効果効能などをうたう場合は、より厳重な注意とチェックが必要となります。
ランディングページを広告として出稿する場合は、薬機法に触れる記述があると広告出稿審査が通らない場合もあります。また内容によっては、薬機法違反など処罰の対象となることもあるのです。
ユーザーの興味を引く表現は、ランディングページのコンバージョンを高めるうえでとても重要なポイントではあります。しかしその表現や文言が適切か、確認したうえで公開することが大切です。記述内容に問題がないか、誇大広告になっていないかなどチェックしてくれる専門サービスなどもありますので、自信がない場合には相談してみると安心でしょう。
ランディングページでは多くの画像を用いて、インパクトを持たせたり印象付けたりすることが多いです。
しかし見栄えの良いページを作ろうとデザインにばかり気が向いてしまうと、本来伝えるべきことがユーザーに伝わりにくいページになってしまうこともあるため注意が必要です。
また多くの画像や過度なアニメーションなどを取り入れることにより、表示速度の低下を招いてしまうこともあります。特にスマホでアクセスしている場合は、表示速度が遅いと離脱の可能性が高まるため注意が必要です。
何もかも全てお洒落にするのではなく、ターゲットや商材、アクセスするデバイスなどにあわせてデザインすることも意識しましょう。
いかがでしたでしょうか?効果の高いランディングページを制作する上で一番大切なのは、「ユーザーの目線」に立つということです。
これを機に、広告を効果的に運用していくためにも、ランディングページを見直してみてはいかがでしょうか?もし現在のランディングページに課題を感じているのであれば、弊社のLPO専門チームに一度ご相談ください!