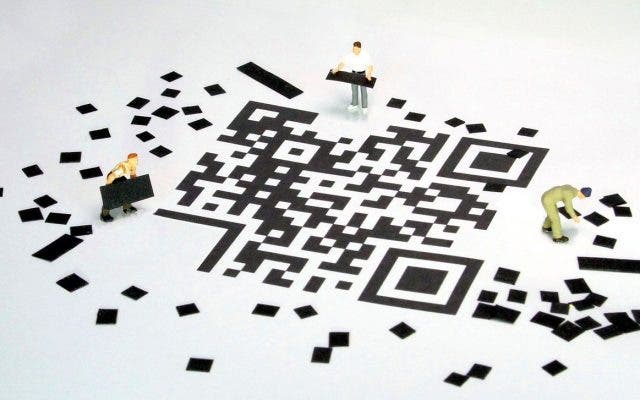
インスタグラムのQRコード(ネームタグ)の表示・加工方法から、スキャン・シェア方法まで解説します
インフルエンサーマーケティング
2022.12.23
2017.03.29
2023.05.31
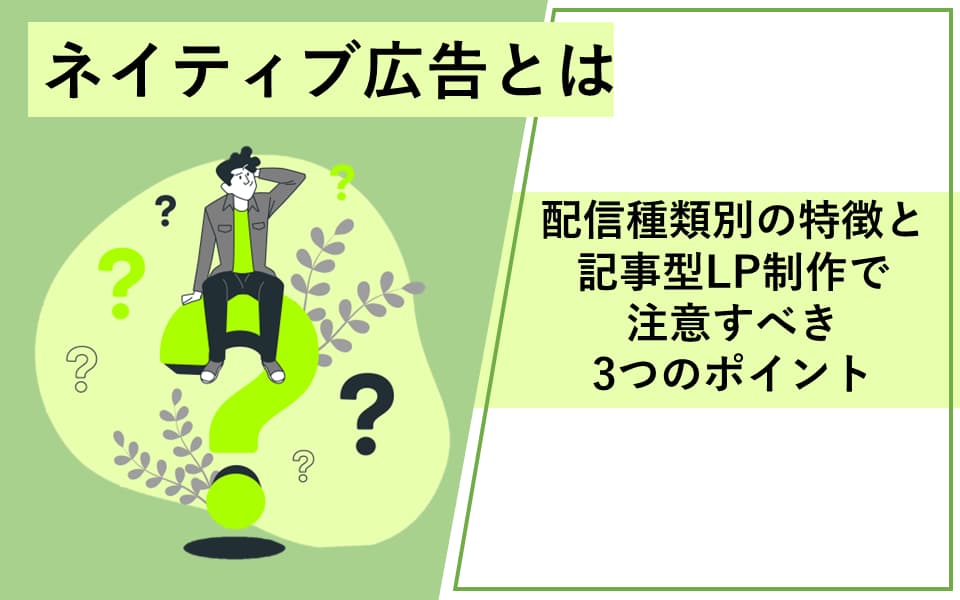
近年、多くの広告主様の間でよく話題にあがるネイティブ広告(ネイティブアド)。
「実際にCV(コンバージョン)はとれているのか」
「広告の種類ごとに意識すべきポイントなどはあるのか」
と疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
今回はネイティブ広告の配信種類別の特徴と、ネイティブ広告用の記事型LPで注意すべき3つのポイントをご紹介します。種類別の特徴を把握し、ベストなネイティブ広告を選択できれば、より効率的に売り上げを伸ばせるでしょう。ぜひ最後までご一読ください。
一般社団法人インターネット広告推進協議会(JIAA)では、ネイティブ広告を「デザイン、内容、フォーマットが、媒体社が編集する記事・コンテンツの形式や提供するサービスの機能と同様でそれらと一体化しており、ユーザーの情報利用体験を妨げない広告を指す」と定義しています。
噛み砕いて説明すると、ネイティブ広告は「Webメディア内の一般記事に溶け込んでいる広告」です。コンテンツの中に自然な形で広告を溶け込ませることで、ユーザーにコンテンツの一部として見てもらえます。
ネイティブ広告は、Webページ上にテキストや画像を貼り付ける「バナー広告」の反応率が下落している中で登場しました。バナー広告で反応しないユーザーにもリーチできる特徴と、ブランドの認知や行動に繋がりやすい2つの特徴があります。
調査データ(全文英語):http://www.ipglab.com/2013/06/18/ipg-lab-sharethrough-exploring-the-effectiveness-of-native-ads/
代表的なネイティブ広告としては、
インフィード型
レコメンドウィジェット型
の2種類があります。
実はWeb広告で一番有名な「リスティング広告(検索連動型広告)」も、IAB※(Interactive Advertising Bureau)ではネイティブ広告と定義されています。
しかし一般的にリスティング広告はネイティブ広告として認識されておらず、ネイティブ広告と言うべきか議論が必要です。
弊社では、
潜在顧客向けのインフィード広告(Amebaインフィード/Yahoo!インフィードなど)
レコメンドウィジェット型広告(logly lift/Outbrain/Yahoo!コンテンツディスカバリーなど)
を中心にネイティブ広告と呼称しています。
ここからは代表的な2種類に加えて、最近利用されるネイティブ広告を4つご紹介しましょう。
※IABとは、インターネットの技術コミュニティ全体の方向性やインターネット全体のアーキテクチャについての議論を行う技術者の集団を指します。

インフィード型は、ソーシャルメディアやモバイルサイト内のコンテンツとコンテンツの間に表示される広告を指します。FacebookやTwitterなどの「SNS系フィード広告」や、前述のAmebaインフィードやYahoo!インフィードが有名です。
SNSの場合は友達やフォロワーの投稿と投稿の間に、メディアの場合は記事と記事の間に広告が表示されます。コンテンツ間に表示されるため、通常のバナーと比べて10倍以上もクリックさせることがあり、人気のある広告手法です。

レコメンドウィジェット型は、ユーザーが普段閲覧しているYahoo!ニュースなどの記事下部に、おすすめコンテンツの形式で表示される広告です。
ユーザーが現在進行形で読んでいる記事に対し、親和性の高い広告が表示されるため、広告であることに気づかれにくい特徴があります。
ペイドサーチ型はいわゆるリスティング広告です。ユーザーの検索語句に連動して、検索結果に表示される広告を指します。
一目見ただけでは通常の検索結果と同じですが、「広告」や「スポンサー」と表記されているため、よく見ると区別可能です。
プロモートリスティング型は、サイト内で検索した際に上位表示される広告です。 ECサイト(Amazonや楽天など)や情報メディア(ぐるなびや食べログなど)の上部に「PR」や「広告」、「スポンサー」表記と共に表示されます。
違和感なく表示されるため、インフィード型と同様にクリック率が高いです。
ネイティブ要素を持つインアド型は、サイト内のコンテンツ内容と関係のある広告を表示する手法です。
潜在顧客にリーチしつつ、サイトを訪れたユーザーの高い満足度を維持できる傾向にあります。しかしデザイン面の親和性が低いため、クリックを避けられやすいデメリットも存在します。
カスタム型はこれまで紹介してきた種類とは異なり、分類が難しい広告を総称したものです。 有名なものは「LINEの企業公式スタンプ」や「記事広告」などがカスタム型に該当します。
カスタム型は、これまで紹介した種類とは異なるため分類が難しい広告を総称したものです。 有名なものでは「LINEスポンサードスタンプ」がカスタム型に該当します。
ただ、カスタム型は分類が難しいことから「そもそもネイティブ広告なのか」が議論されることもあります。
ここまでに、ネイティブ広告の大まかな特徴や種類についてご紹介してきました。とはいえ、「普通の広告と違うことはわかったけど、結局どう使ったらいいの?」と思う方もいるかと思います。
ネイティブ広告の効果を最大限に発揮するためには、正しい理解が不可欠です。 ここからはネイティブ広告のメリットとデメリットを丁寧に解説します。
ネイティブ広告のメリットは次の通りです。
順番に見ていきましょう。
ネイティブ広告を利用することで、自然な形で違和感なくユーザーを誘導できます。配信先のコンテンツや雰囲気に合わせて、広告を配信できるためです。
特にインフィード型は、コンテンツを見ていく中で自然と目に留まり、ユーザーに違和感を生じさせず誘導できるでしょう。 そのため一般的なバナー広告と比べて、CTRが高い傾向にあります。
ネイティブ広告を利用して、商品やサービスの評価を落とさずに、広告を配信しましょう。
ネイティブ広告は、ニーズ顕在化前の潜在顧客や準顕在層にアプローチできる手法です。そのため顧客となりうるターゲットに、幅広く商品やサービスの情報を届けられます。
実際にアトリビューション分析を用いて「初回接触ユーザーを生み出した広告媒体は何か」を調べた結果、驚くほど多くの新規ユーザーがネイティブ広告を見ていることがわかりました。
潜在顧客に幅広くアプローチして、効果的な宣伝を行いましょう。
アトリビューション分析について詳しく知りたい方は、下記記事をご確認ください。
ネイティブ広告は、サイト内の1コンテンツとしてユーザーに認知されます。そのためユーザーが自ら、広告を拡散する可能性があるのです。
広告をユーザーにシェアしてもらえる手法は少なく、一度バズれば予想を遥かに上回る宣伝効果を見込めるでしょう。
拡散を狙う場合は、ユーザーの興味を引きやすい企画が必須です。広告の中身にも力を入れ、効果的な運用を目指しましょう。
ネイティブ広告のデメリットは次の通りです。
それぞれ詳しく解説します。
ネイティブ広告のデメリットとして、コンテンツと勘違いしたユーザーが離脱しやすいことが挙げられます。
コンテンツと広告の区別をつけづらい形で配信するため、広告に嫌悪感のあるユーザーは「え、広告だったのか…」とすぐに離脱してしまうのです。コンテンツに溶け込む広告だからこそ、ユーザーからの印象を悪くしないように慎重な運用を心がけましょう。
広告を配信するサイト内のコンテンツに近い素材を作成する必要があるため、お金と時間がかかります。またコンテンツに合わせるため、既存のクリエイティブがほとんど使用できず流用も難しいです。
ネイティブ広告を運用する場合は、多めの費用を見込んで予算を算出しましょう。
ネイティブ広告は潜在顧客へのアプローチ手法であるため、顕在顧客への広告と比べると、売り上げが出るまで時間がかかります。
ゆえにすぐに結果が欲しい場合は、別の広告を試した方が良いかもしれません。とはいえ長期的にみると、ネイティブ広告はコストパフォーマンスの高い手法だともいえます。
どのような結果を求めるかを十分検討した上で、ネイティブ広告を視野に入れましょう。
ネイティブ広告で重要なのは、バナーやLPなどのクリエイティブを配信先のトンマナにあわせることです。
例えばユーザーが「Yahoo!ニュース」を読んでいて、レコメンド記事欄に全く関係のないバナーが出てきたらどうでしょう?さらにバナー先が、広告色の強い健康食品の定期購入用LPならユーザーはどう思うでしょう?
ネイティブ広告の強みである、自然な誘導が台無しです。
そのためネイティブ広告のバナーを、メディアのトンマナにあわせる必要があります。またクリック先のLPでも、従来LPのように商品やサービスを強く訴求してはなりません。
ユーザーにとって価値ある情報を届けて、最後に商品を紹介する『記事型LP』が重要となります。
Facebook広告やTwitter広告などのSNSインフィード広告の場合は、CTRを高めるためにSNSがどのような目的で利用されているのかを考える必要があります。SNSの主な目的は、ユーザーが個人間でコミュニケーションを取ることです。つまり友達の投稿間に広告を設置するため、ユーザーが投稿するような素材が大切となります。
具体的には、
などです。
逆に商品を強くPRするバナーや、プロのカメラマンが撮影したキレイ過ぎるバナーは避けられる傾向にあります。
YDNやGDNなどのバナー広告で言われる「良いクリエイティブ」と、SNS上に展開すべき「良いクリエイティブ」は性質が異なることを理解して、成功パターンを見つけましょう。
その他のインフィード型メディアでも同様です。
ユーザーがどのような情報を求めてメディアに訪れているのか
メディア内の一般記事のバナーはどのようなものが多いのか
上記のようなリサーチを行った上で、メディア毎に調整したバナーを展開する必要があるでしょう。
ネイティブ広告活用時のバナーについて、上記で触れてきました。次はバナークリック後のLPの注意点を解説します。
ネイティブ広告をクリックするユーザーは、まだ商品やサービスを購入したいと思っていない場合がほとんどです。そのような潜在層のユーザーに「この商品すごくいいですよ!」と強めに訴求しても毛嫌いされるのみ。
大切なことは、クリックしたユーザーが興味を持ちそうな内容であること。また読み飛ばしても内容が理解できるよう、こまめに画像を使用するといった工夫も必要となります。
ユーザーが、最後まで読んでくれる記事の制作を心がけましょう。
商品やサービスの訴求ばかりではすぐに離脱されますが、全くセールスしないと成果(CV)には繋がりません。
ユーザーが商品を購入するためには、購入を判断できるだけの情報が必要です。そのためターゲットユーザーが、商品やサービスを購入する前に知りたいであろう情報を提供することが成果に繋がります。
必要な情報をあらかじめ整理し、過不足なく伝えられるようチェックしましょう。
ネイティブ広告媒体の中には、Yahoo!コンテンツディスカバリーのような審査基準の厳しいものが存在します。そのような媒体で審査に落ちると、確認や作り直しに時間がかかり、必要以上にコストがかかるでしょう。
「他媒体では審査に通過するのに、どうしてこの媒体だけ通らないの!?」といった状態を避けるため、記事広告用LPを制作する場合は
をきちんと確認してから、制作に取り掛かりましょう。
あらためて、ネイティブ広告の種類とメリット・デメリットをまとめておきます。
▶︎ネイティブ広告の種類
インフィード広告
レコメンドウィジェット型広告
ペイドサーチ型
プロモートリスティング型
ネイティブ要素を持つインアド型 (IAB スタンダード)
カスタム型(その他)
▶︎ネイティブ広告のメリット
自然にユーザーを誘導できる
潜在顧客にアプローチできる
拡散されやすい
▶︎ネイティブ広告のデメリット
コンテンツと勘違いしたユーザーが離脱しやすい
コンテンツ作成にお金と時間がかかる
即効性が低く、すぐに利益に繋がらない
ネイティブ広告は数多く存在するため、企業の方針によって全く異なる手法を取ることになるでしょう。そのためネイティブ広告への深い理解が必要となる反面、運用やクリエイティブがハマれば、一気に利益UPへ繋がります。
特に弊社において、ネイティブ広告で効果が出ないと相談されるケースで一番多いのが、ユーザー目線に立てず自分本位なバナー・記事を配信しているパターンです。
配信先媒体のトンマナやユーザーの行動・心理を考えたうえで、バナーや記事型LPを作り込むことが重要といえるでしょう。